ページID:122824更新日:2025年9月30日
ここから本文です。
知事臨時記者会見(令和7年9月25日木曜日)
|
衆議院第一議員会館地下4階第8面談室 13時30分から 発表事項
|
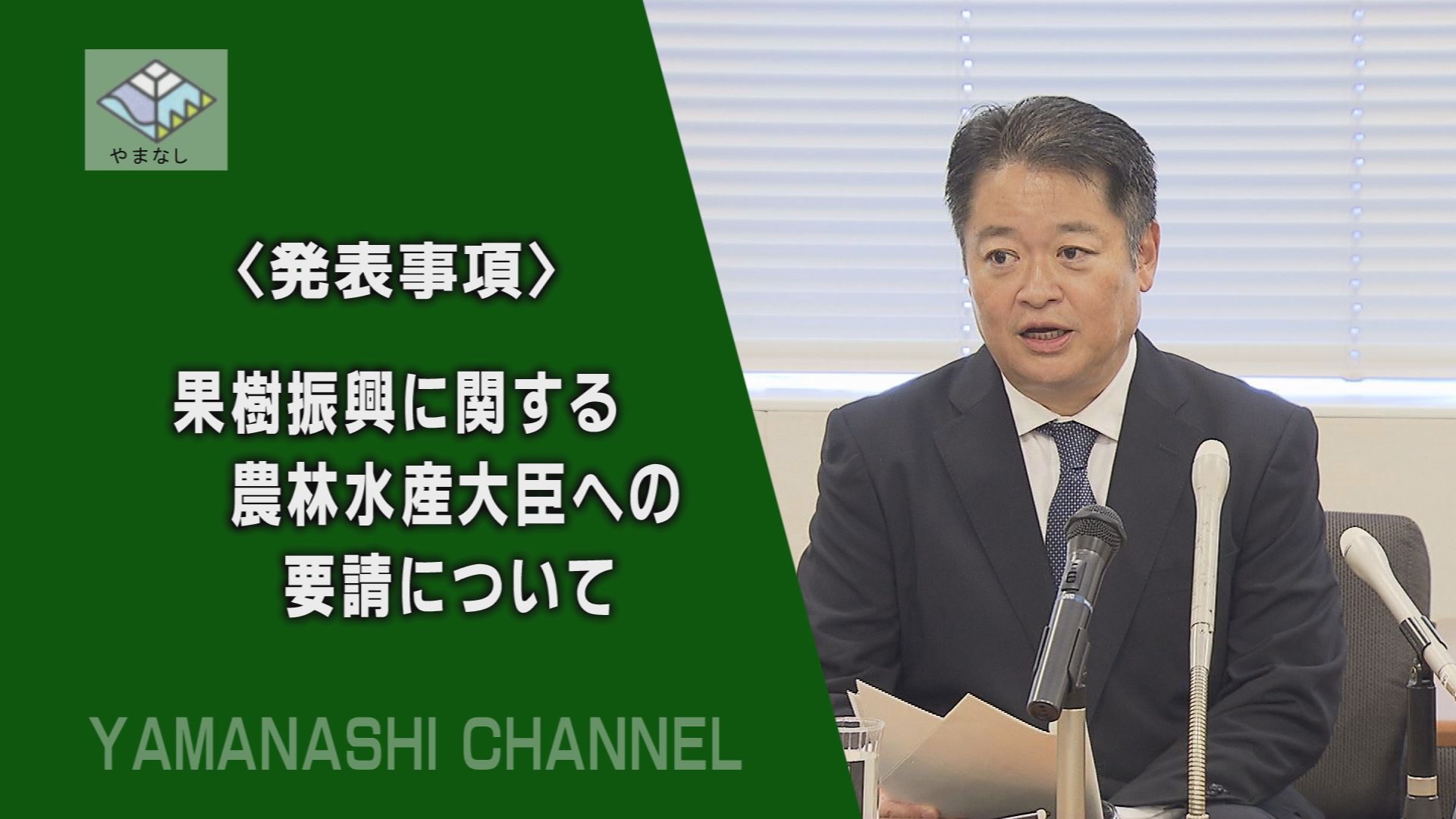 |
小泉農林水産大臣への国産果実の海外戦略に関する要請について
知事
小泉農林水産大臣に対しまして、国産果実、シャインマスカットの海外戦略に関しまして要請を行った次第であります。
ご案内のとおり、近年、海外市場では日本以外で生産された安価なシャインマスカットが広がっております。
こうした状況に対応するため、国内の果樹産地では地域の特性を生かし、懸命にブランド価値の向上に取り組んでいるところです。
こうした中で、先般、農林水産省より、シャインマスカットの海外ライセンス許諾、すなわち海外生産の許諾を行うということで具体的な検討をしている旨の連絡がありました。
農水省からは、国内産地への影響を与えない範囲で運用すると説明はありましたが、私たちとしては、海外のライセンス展開、すなわち、海外生産は国内産地からの輸出環境を整えた後で検討してください、そうされるべき問題だと思っています。
現状、私が県知事になってから6年経ちますが、この6年間の間、少なくとも1ヶ国も新しいマーケットは開いておりません。
他方で、例えば、ブドウに関しましては、ペルーからの輸入が解禁される、スモモに関しては、アメリカからの輸入が解禁される、こういう外からはいっぱい入ってくるのですが、我々から外に出させてもらうことが全くできない状態が続いている。
その中での海外生産ということで、これは当然、山梨だけではなくて、このシャインマスカットは今、日本全国の果樹産地でも大変有力なものでありますが、そういうものを衰退の危機、瀬戸際に追い込んでしまうと思います。
繰り返しになりますが、これから人口減少の中で国内マーケットはどんどん縮小をしていきます。
そうした中で、海外に輸出するということは極めて果樹農業の生き残りのために重要なのですが、その中で、要はその海外輸出ができないような状態のままで、こともあろうに海外に生産させるというのは、我々とすればどこを見て、仕事されているかなと思わざるをえません。
是非、日本の農政は、日本国内の産地ファーストでやっていただきたいと思います。
本当に懸命な努力を国内産地の各農家さんは行っておりますので、産地としては、海外輸出さえさせていただければ、そういう条件をしっかり整えていただければ、この海外生産許諾も別に決して恐れる話ではないわけですが、海外輸出ができない中でパイが奪われてしまうような、こういう状態を作ることはやめてくださいということであります。
今日お出しした要請書の中にはその旨を書きまして、特に海外生産の前に、まずは国内産地が国際市場で平等に競い合える環境を整えていただくこと、これを最優先にしていただきたい。
特に、ベトナムなど新たな輸出国の拡大に向けた、検疫を含む条件整備の加速ということを強く要請しました。
いたずらに反対しているわけではありません。
真に対等な土俵で競争をさせてほしい。
私たちの思いはその1点です。
そこにまずは注力をしていただいて、その上で海外生産許諾でも何でも検討したらいいじゃないですかと。
今日、私たちの思いはこれだけです。
特に、これはおそらくは全産地に共通した思いで、先日も岡山県の知事さんと話をしましたけれども、やっぱり同じように、まず海外輸出をさせて欲しいと。
ここが一番大切な思いでありますので、今日は小泉大臣にはそういう思いをお伝えしました。
大臣からは、産地の理解が得られない状況の中では、この海外生産許諾は進めることはないと、お約束をいただきましたので、私たちとしては、この点について、高く評価したいと思います。
今後、先ほども大臣はじめ農水省の幹部の皆さんと、とにかく輸出が重要だということはよくわかったと、全力を尽くすと、このようなお話もいただきましたので、今後、農林水産省と産地との間で建設的な対話を進め、私たちは繰り返しなりますが産地の農家さんがしっかりと頑張れば報われる、こういう環境づくりに引き続き取り組んでいきたいと思います。
小池会長
知事の仰ったとおりでございますので、ひとつよろしくお願いします。
永井議員
私も同席をさせていただきました。
今回のこの海外ライセンスの許諾ということで、私も色々と、このお話を伺ってから産地をまわって参りました。
本当に不安の声というのがあって、今日、知事からも、そして、また、国会議員の先生方からも、そういった切実な声を大臣に聞いていただきました。
本当に知事がおっしゃるとおり、とにかくその戦える土俵さえいただければ、日本の各産地の果実は、決して負けることはないというふうに思っております。
その努力も、今日、大臣からも、できる限りやって参る。
そしてまた、産地の生産者の意見をしっかりと聞きながら、決して拙速には進めないというお話でしたので、そこは本当に一安心しております。
ですので、農水省にあたっても、一刻も早く、海外のマーケットをできるだけ多く開いていただけるような、そんな努力というか建設的な議論をこれからも進めていきたいと私も思います。
ありがとうございます。
堀内議員
私からも、これだけ農業の産地に山梨県がなってくるためには、多くの農業者の努力と、地元の関係産業の皆様方の努力があったわけでございます。
農業が栄えるというのは、農業が栄えるのではなくて、農業を担っているお一人お一人の努力があって、初めて農業全体の地域のブランド力、そういったものがございます。
そういった意味で、農業者お一人お一人のそういった立場をしっかりと考えていただきながら、国としては、海外との交渉を進めていただきたいというふうに思っております。
記者
幾つかあるんですけども、これ今回、こういった海外ライセンスを進めるという流れというのは、突如、小泉農水大臣のもとで打ち出されたということなのか。
あと、その輸出に関しては、おそらく再三にわたって、山梨県側としても要請していたのではないかなと思いますが、なぜ、皆さんの希望に沿って、輸出が進んでいかない現状になってしまってるのか、その2点お聞かせください。
知事
まずこの話は小泉大臣の前からありまして、私たちも農水省に行って、反対ですということを以前からお伝えしていますが、農水省も粘り強くこれに取り組んでいらっしゃるようです。
それから輸出については、これは植物検疫のいろいろな条件があるんですけれども、優先交渉の順位も、どこに重点を置くかっていうのもあるのかなと思います。
ただ少なくとも、ブドウに関しては、例えば、ベトナムに対して、もう7、8年以上前から輸出するしない、取り組むみたいな話があるにもかかわらず、一向に進んでいない状況があります。
我々としては、もう早く先方の国としっかりと交渉していただいて、できる限り急いで進めていただくように取り計らっていただきたいと思います。
記者
今のお話ですけども、ベトナムに関して7、8年前からお願いをしてると。
なんで7、8年前からお願いしてることが進まないんだっていうふうに知事は思われるんですか。
知事
いや、私もなんでかなと思います。
記者
農水省の機能不全ということでしょうか。
知事
それぞれの果物ごとに、それぞれの国と交渉をするので、どこにそのヒューマンリソースを割くとかそういう問題があるのかなとは思いますけれども、ちょっとなぜ進まないのかは、私はわかりません。
わかりませんし、理解はできないし、耐えがたいと思っています。
記者
その点につきまして、大臣の認識はいかがでしょうか。
なぜこの7、8年もかかってしまうのか、改善されないのかみたいな。
知事
そこはお話しされてません。
記者
お話されていないんですか、わかりました。
大臣の発言としましては、産地の理解がえられない状況では、海外輸出することはございませんよと。
知事
いや、海外生産許諾ですね。
ライセンスを付与することはありませんということでありました。
記者
検討するけれどもと。
知事
はい、検討するけれども、ゴーサインは出さないと。
記者
それ以外に何か大臣発言ございましたでしょうか。
知事
主立ったところはそこですね。
記者
では、もうずっと山梨県側からの要望を聞き置いてるような状況だったという。
知事
途中、農水省の局長さんからのご説明はありましたけれども、それに対して我々から、それは違うんじゃないですかというようなやりとりはありました。
記者
わかりました。
では、ほとんど大臣は喋られてなかったと。
知事
大臣はその農水省の担当の方に、よく説明するようにというお話がありました。
記者
書いていただいてるこの輸出条件の整備のところでもうちょっと詳しく伺いたいのですけれども、何が一番ネックというか、どういった障壁があってなかなか進まないということなのかということをもうちょっとご説明いただきたいのと、それに引き続いて、要するにその対等な土俵で競争という、お気持ちは良く分かるのですが、どこが解消されれば対等な土俵だといえるようになるのかっていうのをちょっとイメージしたいので、もうちょっと詳しく教えてください。
知事
問題は、今の状況では植物検疫です。
日本から持って行く病害虫の問題を科学的に分析することになっていますが、その分析が遅々として進んでいない。
これが1点。
これを急ぐか、急がないかっていうのはおそらくディールの世界なのかもしれませんが、まずはご質問の答えでいうと植物検疫です。
それから、対等の状況がどうかというと、つまりこの植物検疫に基づく障壁を外していただければ、あとは産地の努力の問題なので、我々としてはこの植物検疫だけは、国と国との話なのでどうにもならない。
ここが最大の障壁であり、ここを何とかしてほしいということであります。
記者
今日、小泉さんからは植物検疫について急ぐ急がないとそういう話まではなかったと。
知事
それは我々から再三再四、強く要請いたしました。
特に、ベトナムとの間での植物検疫の交渉は急いでくださいと。
早く妥結してください。
こういうお願いは再三強く言いました。
記者
今日もされたということですか。
知事
もちろん今日も申し上げました。
記者
答えは。
知事
頑張りますというお話でした。
記者
農水省からのシャインマスカットの海外ライセンス許諾の検討が進められてるというお話ですけど、輸出が進んでいない中で、なぜ農水省はこれを進めるべきだというふうに県側に説明しているのかっていう点と、具体的にライセンス許諾の産地、どの国で想定して農水省がライセンス許諾をしようとしてるのかという説明があったのか伺えればと思います。
知事
対象国は、ニュージーランドだと私は理解しています。
ここに何もしないで放っておくと、中国産や韓国産由来のシャインマスカットの苗木が行って、当該国のマーケットを荒らすというか、シャインマスカットに対する、よろしくないイメージができるのではないだろうか。
であれば、日本産由来の苗木を持って行って、ちゃんとした生産をした方が、シャインマスカットのブランドは保てるんじゃないかという説明でした。
ですが、これはナンセンスだと我々は思っていて、苗木と言っても韓国産、中国産由来であろうが、日本産由来であろうが、DNAは一緒なんですね。
何が違うんですかと言ったら、そこでどういう匠の技というか技術で育てるかということです。
それは結局、仮に日本からの技術指導でやったとしても、作るのは現地の方々ですから、日本の農家が行って、そのままずっとそこで作るわけではないわけですから、当然、匠の技の発揮というのは疑問に思うと。
そうした中で、これは日本産由来ですと言って、日本のブドウブランドをかぶせてしまうことで、逆に我々が匠の技で作っている国内産のブドウのブランド価値というものを毀損するんじゃないかと私たちはそう思いました。
記者
ブランドが毀損されるんじゃないかという懸念が、ということなんですが、すでにこういう弊害が、海外ではシャインマスカットが、多分ものすごく日本でも人気なので、海外はもうきちんとライセンスを供与していないのに、似たような模造品が出てるとか、そういう事例があるのかということと、それからやはり、今10月4日の総裁選にかけて、日本の農政がどうなるかっていうことも1つの重要なポイントだと思いますが、小泉大臣のみならず、他の4候補にも求めたいという点が、ここもあれば、ぜひお聞かせいただきたいです。
知事
1つは、シャインマスカットの現状ですが、残念ながら中国、韓国では、普通に生産されています。
これは許諾しないで、ある意味勝手にされてしまう。
それに対する権利の保全の仕方が甘かったのだと思うんですね。
もともとこれは日本産由来ですから。
農水省が開発したものなんですけど、その権利の保全の対策がぬるかったんだと思います。
であるがゆえに、結局、今、中国では多分全省で作っている。
韓国に至っては、シャインマスカットを作ったのは日本だけれども、世界に広めたのは俺達だと言っているんです。
こういうのが今の現状です。
実際、他の国、例えばベトナムを見ても、韓国産のシャインマスカットを売っていますけども、我々からするとショックを受けるぐらい美味しくないものであることは間違いない。
なので、輸出さえさせていただければ、十分戦えると思っています。
そういう状況が1つと、総裁選との関係でも、今日は総裁選を念頭に置いてやってるわけではありませんが、まず、農水大臣がご担当なものですから、お願いしようということで、その方がたまたま今、総裁選に出られてるということと、あと、私たちは明日は官房長官に同じ要請をしていきたいと思っています。
記者
ライセンスの海外展開によって、日本の生産農家などがどういう影響を受けるのか、みたいな話は農水省からあったか。
知事
農水省からは、「ライセンスフィーによって新たな品種の開発に役立ちます」と、こういうご説明ではありましたが、それはそれで別途予算を取ってやっていただくべき話だと、私は思います。
他方で、これが南半球で作られて、それがある程度世の中に出回るようになると、1つはシャインマスカットの値段は出した当初の希少性でハウスで作られたものがすごく単価が高いんですね。
ハウス農家は、組合長のお話ですと、まさに匠中の匠の方々なのですが、その方々がまず打撃を受けるのです。
希少性がなくなるので。
当初の高い値段が、平準化してしまって、下がってしまうのですね。
そうすると、せっかくそのコストをかけてやってきたハウス農家、イコール匠中の匠の方々の経営が大きな打撃を受ける、これを我々は心配しています。
さらに、今は保存技術が進んでいて、一年中とまでは言いませんけれども、12月以降も出せるのです。
「クリスマスシャイン」といって山梨県では出していて、他の県でもやっていると思いますけども、こういう状態なので、北半球・南半球で完全にすみ分けることなんてできないのです。
どうやっても国内産地には影響が及ぶ。
いいことはない。
開発するのだったら、その資金ぐらいは別途予算を取ってやればいいので。
なければ、山梨県から国に対して補助してもいいぐらいです。
産地が受けるマイナスというのは現状においては極めて大きいと思います。
輸出さえさせていただければ。
繰り返しなりますが。
記者
彼らも影響が大きいというふうには思ってないのか。
知事
思っていない。
記者
もう1点。
明日、また官房長官にお会いして、輸出に関してこのままだらだらと改善が行われない場合、知事は次にどう行動に出るのか。
知事
海外マーケットが開くまでは徹底抗戦です。
記者
具体的にはどんな感じで。
知事
全国の産地を糾合して抗議活動だと思います。
海外産地を優遇して国内産地をないがしろにするなど、あり得ないわけです。
農業は我々地方にとって、その土地に住む意義そのものであり、そこに住む意味を見出しているわけです。
その意味を破壊しかねないような動きに対しては、徹底抗戦だと思います。
記者
徹底抗戦などと言わしめるシャインマスカット。
山梨県にとってのシャインマスカットはどういう存在でしょうか。
知事
山梨県の象徴だと思います。
岡山県さんも同じことを考えてると思います。
それぞれの産地が汗水垂らして、いろいろな工夫を積み重ねて作ってる県の宝物であり、象徴であり。
ちなみに最近、シャインマスカットを作ろうということで、山梨県では新規就農者が毎年300人から400人、過去数年間ずっと出続けているのです。
それだけ、やはりこの土地に住む意味というのをつくり出してる、すごい重要な産品だと思っていますので。
そういう意味で、お米も重要な日本にとっての農産品だと思いますが、山梨県や他のブドウ産地にとって、シャインマスカットはやはり同じぐらいの意味を持つ、大変重要な農産物だと思っています。
記者
小池一夫さん、農業協同組合中央会長の方もいらっしゃっているということで一言、シャインマスカットのライセンスよりも前にまず輸出をという、今、知事の話で出ましたが、小池さんの思いを聞かせていただけますか。
小池会長
先ほど来の知事からの説明がすべてだと思いますが、私ども農業者という立場からして、やはり山梨県の特異性ということがあると思います。
関東平野とか、平野で農業をやっているわけではなく、そういった広いところがあれば土地利用型の農業ができますが、山梨県の農業は、昨年の山梨県の発表によると、生産額が1,239億8,000万円でしたが、そのうち、何と果樹が769億、野菜が174億ということで、75%を果樹と野菜で占めてます。
水田を耕作できるような平坦地が少ないものですから、78億ぐらいしか水稲が栽培できないということで、いわゆるお米は消費県です。
そういったところで、傾斜地を利用しての農業をやっているわけでありまして、世界農業遺産に4年ほど前になりましたが、傾斜地を利用した中で、長い間苦労しながら栽培をしていることが認められた訳です。
遺産というと古いもののように思われますが、山梨県の場合、峡東地域の農業遺産は、現状も農家がそこで生活をしながらやっています。
そのようなことからすると、やはり、私どもは長い間の今までの経験を生かして、技術を持って今後も進めていくという自信もありますから、知事が言ってるように、同じ土俵の上で、勝負したいということです。
いずれにしても、私どもは、同じ農業でも、他の県と、あるいは他の国と違ったやり方でやってるということでありまして、そういった特異性がありますので、そういう旨をご理解いただく中でお願いしたいと思います。
