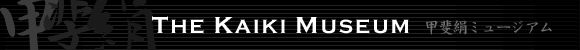
甲斐絹(かいき)のふるさと、山梨。 全国でも高級絹織物産地として知られた、ここ山梨県郡内地域(富士北麓・東部地域)では、産地のシンボルとして『甲斐絹』という織物の名前がひんぱんに耳にされます。 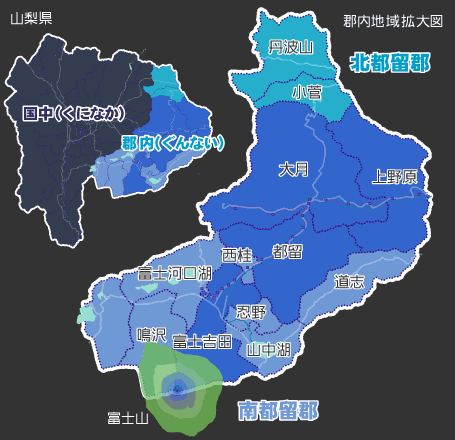 ではこの『甲斐絹』とは、いったいどんな織物なのでしょうか。 おそらく名前を聞いたことはあっても、実際に手にとって見たことのある人は、山梨県の織物産地の中でさえ多くはないのではないかと思われます。 実は、甲斐絹が最後に織られたのは1940年代のこと。甲斐絹は、羽織などの和服が日常的に使われていた時代の終焉とともに、姿を消してしまった織物なのです。 ここでは、幻の織物ともいわれる甲斐絹がどのようなものだったのかを、解説していきたいと思います。 ●・b斐絹の風合いと用途 甲斐絹を手にとると、非常に軽く、平滑な薄手の生地でありながら腰があり、また独特の光沢とサラッとした風合いを持っていることが分かります。
こうした風合いが好まれ、甲斐絹は羽織の裏地に用いられる高級絹織物として、江戸時代から昭和初期にかけて盛んに生産されてきました。
第二次大戦前後、織機や染色機などの自動化や機械化が進んでゆく中、熟練した職人が手織機を使い、手仕事でなければ織ることができなかった甲斐絹の製造は、次第に困難になっていったものと思われます。 しかし、甲斐絹そのものはもう製造されていませんが、山梨県郡内の織物産地では、現在でも甲斐絹の伝統技術をしっかりと受け継ぎ、『先染め・細番手・高密度』の絹織物を得意とする全国でも有数の高級絹織物産地として知られています。 ●製法上の特徴 文献によると甲斐絹の製法は、「経(たて)は経枠(へわく)を用いてへるをよしとし、へて後練り、練りて後染、染めて後乾かし、乾かして後糊をなし、糊をなして後筬(おさ)ぬき、然る後これを巻く」とあります。
甲斐絹の製法では、上図で経糸をあつかう部分(上図の1、6、7)で特徴的な工程が見られます。
この中でとりわけ特徴的なのが、「絵甲斐絹」で見られる、織機上で経糸に加えられる絵付けの工程です。経糸だけに絵柄を付ける製法には、現在行われている「解(ほぐし)織り」もありますが、解織りの場合はいったん仮織りをしたものに絵柄を付けてからこれを解して経糸だけを織機に掛け直すのに対し、絵甲斐絹では、織機に経糸が掛けられたままの状態で型染めを行います。このため、解織りよりも経糸のズレ幅が小さくなり、輪郭明瞭な絵柄をなすことができます。
|
copyright(C) 2003 Yamanashi Industrial Technology Center, All rights Reserverd.
*このホームページの全データについて無断複製・転用をいっさい禁止致します*


