更新日:2025年2月5日
「子育てしやすさ日本一」を目指す山梨県!パパの育児参加を積極的にサポート

ここから本文です。
山梨県は「子育てしやすさ日本一」の実現を目指しており、県庁でも男性職員の育休取得を推進中で、取得率は9割を超えている。パパの子育て参加を積極的に応援しており、2024年12月には甲府市内でプレパパ向けセミナーを初開催。8組の夫婦が参加した。
育児用品より心の準備を!プレパパ向けセミナー開催
プレパパ向けセミナー「赤ちゃんが生まれてくるまでにできること・生まれてからできること」の会場には、次々と参加夫婦が集まってきた。
このセミナーは、父親の育児参加の重要性を認識してもらうと共に、オムツ交換やミルク作りなどの体験を通して、父親としての実感や子育ての正しい知識を深めてもらうことを目的に県が企画したもの。講師を務めたのは、元保育士で3児の父であるNPO法人おっとふぁーざー代表の舘直宏(たちなおひろ)さんだ。
「今日は“がんばりましょう”と言いに来たわけではありません。子育てを楽しんでほしい。でも楽しむためにはコツが必要。それをお伝えします」と舘さんはやさしく話し始めた。
舘さんいわく、育児用品の準備も必要だが、物以外の心構えがさらに重要とのこと。とくに出産時や赤ちゃんが生まれてからの生活について、具体的にイメージして話し合っておくことが大切だという。

「たくさんの話をしてしまいましたが、一度でも聞いたことがあると、必要なときに『あ、そうだった』と思いだせる瞬間があるはずです」と講師の舘さん
出産時の備えとしては、病院への搬送手段を最低でも3つ確保しておくと安心だ。「救急車を含めて、タクシーや親族など、複数の選択肢を持っておいてください。そういう時に限ってトラブルが重なることがあるんです」と舘さん。ほかに出産への立ち合いや里帰りについても事前に検討しておきたい事項だ。ちなみに最近は60代の親世代が現役で働いていることが多く、里帰りをしない人も増えているという。
パパに向けては、「ママは命をかけて新しい命を生み出そうとしている。赤ちゃんも命をかけて生まれてくる。パパは、正直ほとんど何もできません。でもパパがそばにいるからこそ、ママも赤ちゃんもがんばれる」と舘さん。同時にママたちへは「出産の時、パパにできることは多くなくて、むしろ戸惑うことの方が多いので心配になるかもしれませんが、パパも気持ちはママと一緒だということをママに理解してほしいのです」と話した。

ポットに用意したお湯を適温に調整してミルク作りに挑戦するパパたち
親になる実感にはどうしても男女差がある。「ママはつわりや体型の変化、出産の痛みを経験することで、すぐに母親としての実感が湧きやすい。一方、パパは突然目の前に赤ちゃんが現れるような感覚に近く、最初は戸惑いがあります。ただそれも数カ月で追いつきますから、ママには待っていてほしいんです」
後半は実技講習。パパたちは人形を使った沐浴やオムツ交換、ミルク作りに挑戦。慣れない手つきながらも、みな真剣な表情だった。
最後に舘さんは、「思い通りにならないことが子育ての基本です。でもそのイレギュラーを楽しむくらいの気持ちでやってほしいですね。子育ては20年くらい続く長丁場。楽しまないとしんどくなります」と参加者たちにエールを送った。

「オムツをはかせるときにはギャザーを外に出して広げてくださいね」と細かなアドバイスも
パパとしての実感を持つ難しさ
4月に双子の赤ちゃんが生まれる予定の本多さん夫婦は、妻の真理さんが県のチラシを見つけ、夫の仁さんを誘ってこのセミナーに参加したという。「オムツの替え方もミルクの作り方も初めて知ることばかりでした」と仁さん。「赤ちゃんがいる暮らしや父親になることへの実感がまだふわっとしていましたが、具体的に考えるきっかけになりました。細かな不安はありますが、家族が増えることが本当に楽しみです」と明るい声で話した。
真理さんは「双子の子育てはパパに求められる役割がより多いと思うので、上手に連携していけたら」と期待を寄せる。「これまで、どうしてつわりのヒドさを分かってくれないの?とイライラする時も正直ありましたが、男性の立場からの話を聞いて、仕方ない部分もあるのだと理解できました」と穏やかに話した。仁さんは育休も取得予定。二人三脚で育児に向けて準備を進めている。

「細かな不安はありますが、家族が増えることが本当に楽しみです」という本多さん夫妻
講師を務めた舘さんは、「子育てには絶対にがんばらなければならない場面があります。だからこそ普段は楽しむことを大切にしてほしいですね」と力を込める。「毎日子どもと一緒にいると幸せを実感しにくくなりますが、初めて赤ちゃんが立った瞬間や、常にどこに行くのにもべったりだった子どもが成長して『一緒に買い物に行かない』と言い出すような変化に寂しさと嬉しさが入り混じる複雑な喜びがあるんです」と語る。
また、「男性は能力がないわけではなく、ただ分からないだけ。その"分からない"に寄り添い、背中を押してあげれば、きっとできるはず」と言い、「私の話は助産師さんや保健師さんと変わりません。でも男性の口から男性に向けて話すことで伝わることもあるはず。男性が男性をサポートする仕組みがもっとあってもよいのではないかと思います」と話した。ちなみに舘さんは2カ月に1回ほど山梨県を訪れているそうで、「ほどよく都会と田舎があって、富士山が見える風景は憧れ。移住政策も進んでおり、子育てしやすそうな環境ですね」とほほ笑んだ。

「男性が男性をサポートする仕組みがもっとあってもよいかもしれません」と舘さん
企画した山梨県子育て支援局子育て政策課課長の篠原孝男さんは、「夫婦だけで子育てをする世帯が増え、産後うつなどの問題もある中、父親の役割は重要。子育てしやすい社会を作っていくためには父親も積極的に家事や育児に参加していくことが大事だと思います」と背景を説明。
同課主任の田中悠登さんは最近3カ月間の育休を取得したばかり。「子育てをする中で、父親は子どもと一緒に成長しながら父親になっていくことを実感しました。その過程での本セミナーのような学びの機会はまだまだ少ないですね」と語る。
企業にとっても育休制度の充実は人材確保や社員のモチベーション向上につながる。篠原さんは「子育てしやすい社会作りには、父親の積極的な参加が欠かせない」と言い、田中さんも「上司世代の理解も含め、職場全体で支える環境作りも重要です」と続けた。
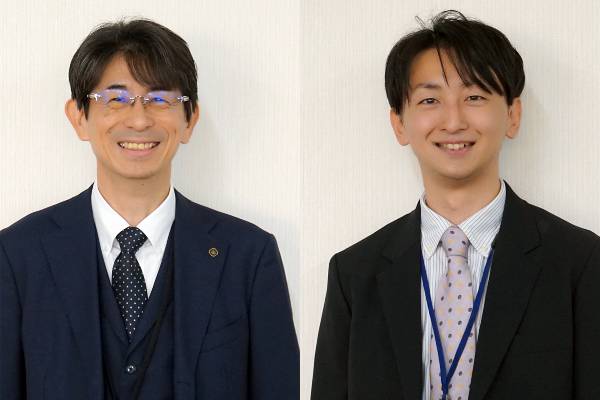
山梨県子育て支援局の篠原さん(左)と田中さん(右)「今後も子育て支援全般に力を入れていきます」
山梨県の子育て支援制度
山梨県では、本セミナー以外にも、出産後を支える子育て支援制度を多数用意している。
乳幼児医療費の助成
通院や入院にかかる医療費を助成する。年齢や助成内容は各市町村による。
病児保育の広域利用
病気にかかった子どもを預けられる病児保育施設を20施設用意し、共働き世帯をサポート。
県内すべての病児保育施設を自由に利用できる「病児保育の広域利用」が可能。
やまなし子育て応援カード事業
18歳以下の子どもや妊娠中の方がいる家庭を対象に、県内の協賛店舗で様々な特典が受けられるカードを発行。
山梨県の男性育児休業取得促進の取り組み
男性が育児休業を取得しやすい職場環境づくりを促進するため、山梨県内の中小企業事業主が実施する雇用環境整備の措置に要する経費に対して助成。
取材を終えて
子育てはママが主体というイメージは、少しずつ変わりつつあるのかもしれない。今回のセミナーも夫婦が一緒に学び、話し合うきっかけになっていた。男性の家事育児への参画の意識が高まっている昨今、こうした取り組みが夫婦で子育てを楽しめる社会を作り、父親の育児参加を後押ししていくのだろう。
取材・文:古屋江美子(山梨県甲府市出身・やまなし大使)




このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
トップ > 組織案内 > 人口減少危機対策本部事務局 > 人口減少危機対策課 > 山梨県人口減少危機対策特設サイト > 特集記事一覧 > 「子育てしやすさ日本一」を目指す山梨県!パパの育児参加を積極的にサポート