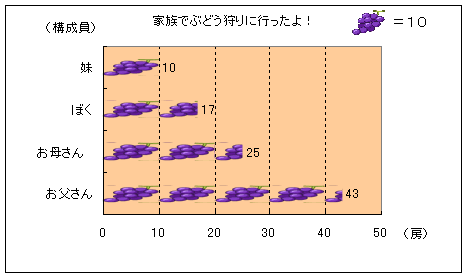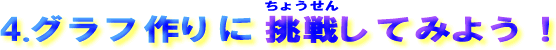| 

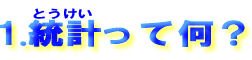
統計とは、ある集まりについて、その集まりが持っている特徴や性質を調べた結果を、その集まりに関する特徴や性質を伝える数字のこと。 たとえば、
① 5年2組全員の中で、好きなスポーツを調べた結果
《好きなスポーツ(5年2組)》
| バレーボール |
サッカー | 水泳 |
その他 | 合計 |
| 4人 |
13人 | 10人 |
8人 | 35人 |
② 8月1日の2時間毎の気温を測った結果 《8月1日の気温しらべ》
| 6時 |
8時 | 10時 |
12時 | 14時 |
16時 | 18時 |
20時 |
| 23.7℃ |
25.6℃ | 28.7℃ |
31.1℃ | 32.8℃ |
30.8℃ | 28.1℃ |
26.5℃ | ③ 耕地面積のうち、田と畑の面積と割合を調べた結果 《田と畑の面積と割合》
| 項目 |
田 | 畑 |
合計 |
| 面積 |
9,270ha | 16,900ha |
26,170ha |
| 割合 |
35.4% | 64.6% |
100% | ▲ 最初にもどる 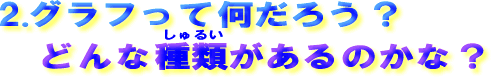
グラフとは・・・
数や量の関係を、全体が一目でわかるように線や図形で表したもの 
グラフには、単位グラフ(絵グラフ)・棒グラフ・折れ線グラフ・円グラフ、帯グラフなどいろいろなグラフがあります。表したい統計データの特徴によって、グラフを使い分けます。 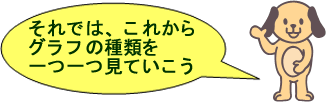
○単位グラフ(絵グラフ)
数量などを絵で表現するグラフです。グラフを見る人に興味や親しみを感じさせます。
<単位グラフを作る時の注意点>
◆絵は同じ形、同じ大きさ、同じ単位のものでそろえましょう。
形、大きさ、単位が違っていると、一目で数字の大小を把握することが難しくなります。
(たとえ同じ形でも、小さな絵が1で大きな絵が10など、2つの異なった単位の絵は使わないようにしましょう)
◇一つの絵を1単位とした場合、その半分は、絵を半分にして表します。
◆1つの絵の単位(数値)を示す凡例を必ず表示しましょう。
◇絵の始まる位置はきちんとそろえ、絵は同じ間隔で並べましょう。
◆絵の最後に数値を表示すると分かりやすくなるでしょう。 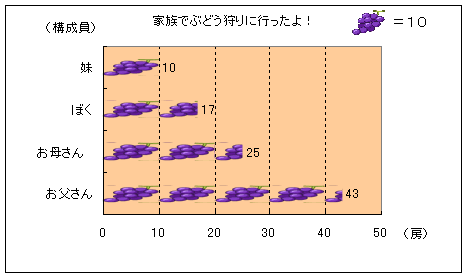
○棒グラフ
数や量を棒線の長さで表し、違いを一目でくらべられるようにしたグラフです。  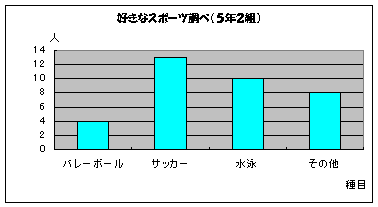 
どのスポーツを好きな人が多いか、好きな
スポーツの順番などがわかります。
○折れ線グラフ
時間の変化とともに、数や量がどのように変化するかを、折れ線で表したグラフです。 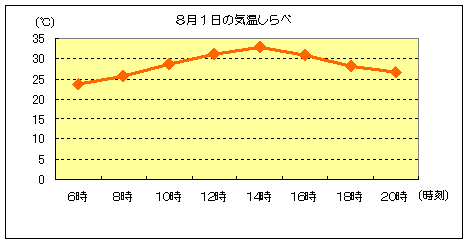
1日の気温の変化がわかります。
○円グラフ・帯グラフ
数や量の大小を円や帯の面積の大小にくぎって、全体と部分の割合や、部分どうしの割合をくらべられるようにしたグラフです。各部分の割合をたすと合計が100%になります。 円グラフ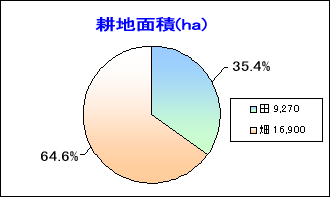
帯グラフ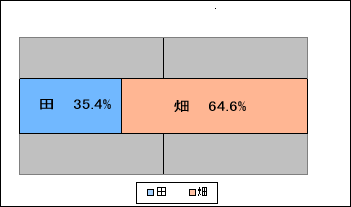
田・畑の面積が耕地面積全体に対してどのくらいかがわかります
また、田の面積と畑の面積の割合がどのくらい違うかもわかります
▲ 最初にもどる
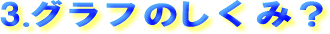
グラフは、いろいろな部分からできています。
たとえば、棒グラフや折れ線グラフを例にとると、つぎのような部分からできています。 (1)表題
グラフの名前、グラフの内容を簡単に表したことば。「好きなスポーツ調べ(5年2組)」、「8月1日の気温しらべ」、「耕地面積」など (2)0線(基線)・縦の基線・横の基線
グラフの基となる縦と横の軸線を、縦の基線、横の基線という。一般には、縦線は左端・横線は下端、目盛りの最下部は必ず「0」とする。
★0線(基線)は、統計グラフには必須という決まりがあるので必ず書こう!
(3)目盛り数字
それぞれの目盛りが示す大きさの値 (4)目盛り単位
目盛り数字の単位。「人」、「種目」、「℃」、「日」など (5)目盛り線
それぞれの目盛りに引かれた線 (6)出典
グラフのもととなる資料の出所、使用しようした本や資料の名前 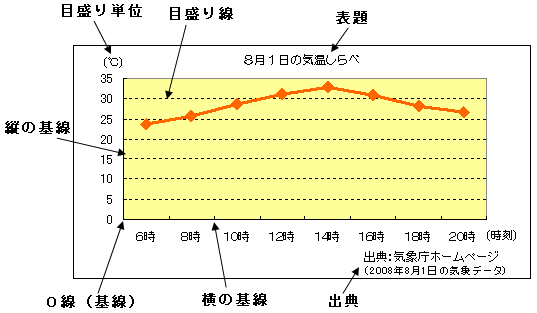
▲ 最初にもどる
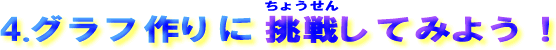
① テーマ(主題)
を決めよう
何をグラフにしたいか考えてみよう!
→統計グラフを使って人に何を訴えたいですか?
→何をわかってもらいたいですか?
② 資料を集めよう
(1)アンケートをとったり、観察したりしてみよう!
(2)本や雑誌、新聞、インターネットなどで調べてみよう!
(3)図書館なども利用しよう!
③ 調べたことなどを表に整理してみよう
(1)アンケート、観察の場合、次のことを表に書こう!
○いつ調べたか
年月日や期間など
○対象者は誰?それとも何?
クラスの人、家族、通行人、自然のもの、車など
○その数は?
何人?いくつ?何台?
(2)本や雑誌、新聞、インターネットなどの場合、調べたことといっしょに、次のことも 必要だよ!忘れずにちゃんと整理しておこうね!!
○資料名
本の名前や調査名
○いつ頃の資料か
その資料はいつ頃調べられたもの?(調査した年や月日)
④ グラフを選ぼう
調べたことを表現するのにふさわしいグラフは何?
グラフの種類はたくさんあり、それぞれに特徴があるよ。
(グラフの説明へ戻る)
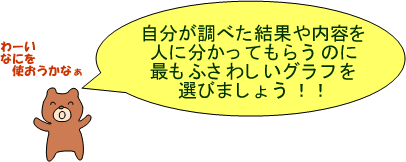
⑤ 表題や副題を考えよう
表題、見出しは作品の中で最初に見る部分、目立つ部分です。
表題を決めるときは、人に訴えたいこと、わかってもらいたいことを簡単にわかりやすく、また見やすく、人をひきつける工夫をして表現しましょう。
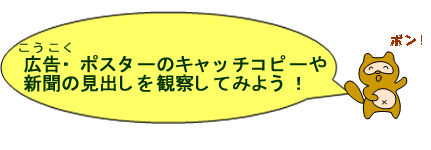
⑥ 図面構成を考えよう
グラフ、表題などの位置とそれらが占める広さのバランスを考えましょう。
その際、一番伝えたい項目は何か、それはどこに置くのがもっとも人の目をひくかを考えましょう。
⑦ 下書きをしよう
「縦と横の基線」を引いたり、「目盛りの単位」や「1目盛りの大きさ」を決めてから、下書きをします。
下書きをすると、イメージが現実に近づきます。色の使い方や文字の大きさなどを考えながら下書きをしてみましょう。
このとき、選んだグラフと表現したい内容が合っているかも確認しましょう。
また、下書きがすんだら、他の人に見せて意見を聞いてみましょう。改善した方が良い点や新たなアイデアがでるかもしれません。
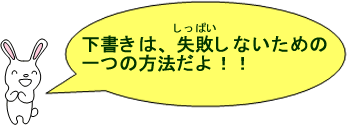
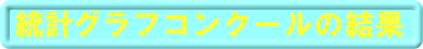
↑ここをクリック!
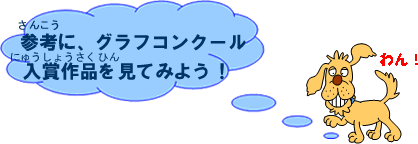
⑧ 仕上げ
(1)塗った絵の具や張り紙がはがれないようにしよう。
(2)作品には裏面に板張りをしたり、表面にセロハンなどでカバーをしてはだめだよ。
(3)③で作った資料を作品の下に貼り付けよう。
(4)誤りはないかな?
→文字、数字、単位、目盛りなど
(5)書き落としはないかな?
→グラフの基になる資料の出所、観察・調査の方法など ▲ 最初にもどる
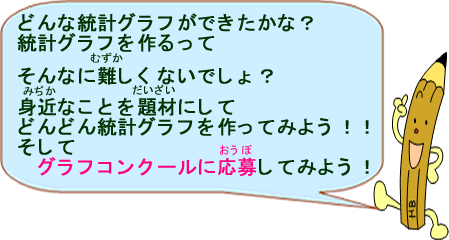
やまなしのとうけいきっずへ
 
| 
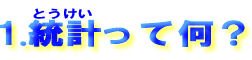
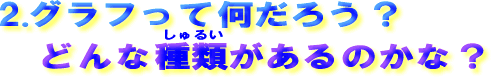
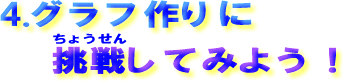

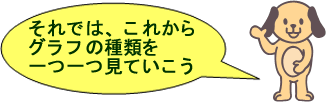

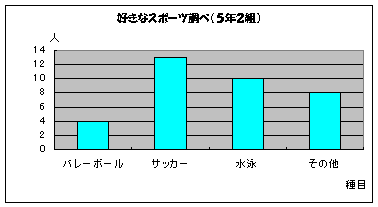

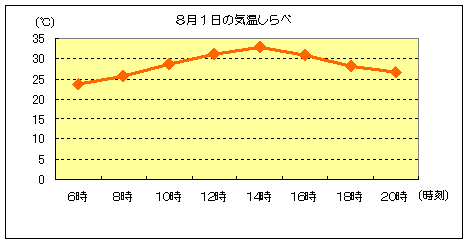
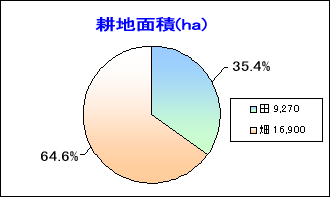
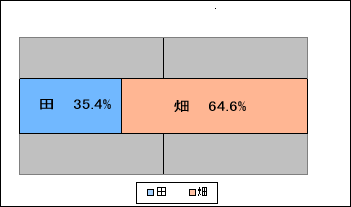
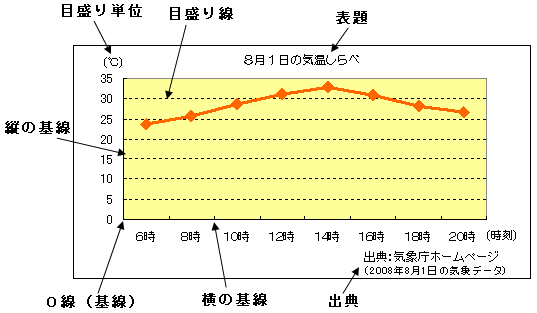
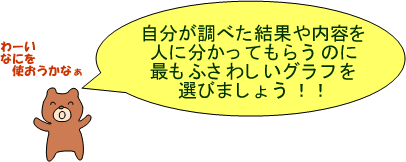
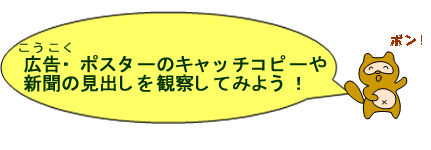
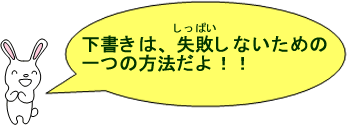
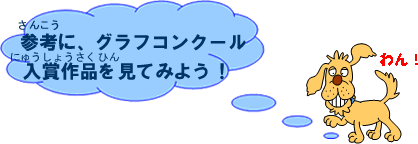
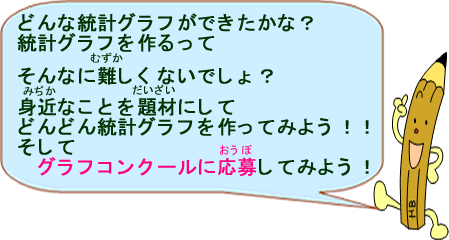
![]()