平成11年 商業統計調査結果報告
1.調査の目的
商業統計調査は、全国の卸売・小売業を営む事業所を対象として、業種別、規模別、地域別等の状況を調査し、商店の分布状況や販売活動を把握することにより、商業の実態を明らかにすることを目的とする。
ページの先頭へ戻る
2.根拠法規
統計法(昭和22年法律第18号)及び商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)による。(指定統計第23号)
ページの先頭へ戻る
3.調査の期日
平成11年7月1日現在。 なお、これまでに実施した商業統計調査の年次別の調査期日は次のとおりである。
|
回
|
調査年次
|
調査期日
|
種別
|
回
|
調査年次
|
調査期日
|
種別
|
|
| 1 | 昭和27年 | 9月1日 | ① | 13 | 昭和51年 | 5月1日 | ① | |
| 2 | 昭和29年 | 9月1日 | ① | 14 | 昭和54年 | 6月1日 | ① | |
| 3 | 昭和31年 | 7月1日 | ① | 15 | 昭和57年 | 6月1日 | ① | |
| 4 | 昭和33年 | 7月1日 | ① | 16 | 昭和60年 | 5月1日 | ② | |
| 5 | 昭和35年 | 6月1日 | ① | 昭和61年 | 10月1日 | ③ | ||
| 6 | 昭和37年 | 7月1日 | ① | 17 | 昭和63年 | 6月1日 | ② | |
| 7 | 昭和39年 | 7月1日 | ① | 平成1年 | 10月1日 | ③ | ||
| 8 | 昭和41年 | 7月1日 | ① | 18 | 平成3年 | 7月1日 | ② | |
| 9 | 昭和43年 | 7月1日 | ① | 平成4年 | 10月1日 | ③ | ||
| 10 | 昭和45年 | 6月1日 | ① | 19 | 平成6年 | 7月1日 | ② | |
| 11 | 昭和47年 | 5月1日 | ① | 20 | 平成9年 | 6月1日 | ② | |
| 12 | 昭和49年 | 5月1日 | ① | 21 | 平成11年 | 7月1日 | ②※ |
※平成11年調査は簡易調査
ページの先頭へ戻る
4.調査の範囲
日本標準産業分類「大分類I-卸売・小売業、飲食店」に属する事業所のうち、飲食店を除く事業所。
ただし、次に掲げるものは除く。
- 国及び地方公共団体に属する事業所。
- 駅の改札口内、劇場内、運動競技場内等、有料の施設内に設けられている事業所。(公園、遊園地、テーマパーク内にある別経営の事業所を除く)
また、以下に該当する事業所等については、9年調査と取り扱いが異なっている。
- 化粧品の訪問販売会社の営業所、代理店は卸売業とし、訪問販売レディはその自宅を小売業として把握。
- 季節営業の事業所については、調査日に専従従業者がいれば調査対象。
- 露店・行商等営業の場所が一定しない又は固定設備がない事業所は、自宅を小売業として把握。
5.調査の単位
調査の単位は、「場所ごと」に「経営者ごと」に行う。
ページの先頭へ戻る
6.調査の方法
調査は、申告者(商店)が自ら記入する方法(自計方式)による。
ページの先頭へ戻る
7.調査経路、調査方法
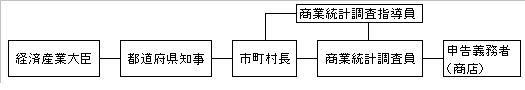
ページの先頭へ戻る
8.主な用語の説明
- 商 店
ここでは卸売業と小売業をいう。 - 卸売業
卸売業とは主として次の業務を行う事業所をいう。- 小売業者又は他の卸売業者に商品を販売する事業所。
- 産業用使用者(工場、鉱山、建設、官公庁、学校、病院、ホテルなど)に業務用として商品を販売する事業所。
- 製造業者が別の場所に経営している、自社製品を卸売する事業所。
- 商品を卸売し、かつ同種商品の修理を行う事業所。
- 他人または他の事業所のために製品の売買の代理行為を行い、又は仲立人として商品の売買のあつせんを行う事業所。
- 小売業
小売業とは主として次の業務を行う事業所をいう。- 主として個人用又は家庭用消費者のために商品を購入し、販売する事業所。
- 商品を小売し、かつ同種商品の修理を行う事業所。
- 製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に小売する事業所。
- ガソリンスタンド。
- 主として無店舗販売を行う事業所で、主として個人又は家庭用消費者に小売する事業所。
- 法 人
会社(株式、有限、合資、合名)、農業協同組合、生活協同組合、その他の法人をいう。 - 個 人
個人経営の事業所をいう。 - 従業者
平成11年7月1日現在で、その商店の業務に従事している個人事業主及び無給家族従業者、会社及び団体の有給役員、常用雇用者、他の会社など別経営の事業所へ派遣している人又は下請けとして別経営の事業所に行っている人をいう。 - 年間商品販売額
平成10年4月1日から平成11年3月31日までの1年間の商品の販売額。 - 売場面積
平成11年7月1日現在で、小売業商店が商品を販売するために実際に使用する売場の延床面積をいう。(ただし、牛乳小売業、自動車小売業、畳小売業、新聞小売業及びガソリンスタンドは除く。) - セルフサービス店
売場面積の50%以上についてセルフサービス方式を採用している商店をいう。
セルフサービス方式とは以下の条件をすべて満たしている場合をいう。- 商品が無包装のまま、あるいはプリパッケージ(消費単位に合わせてあらかじめ包装)され、値段がつけられていること。
- 店に備え付けられた買い物かご・ショッピングカートなどにより、客が自分で取り集めるような形式をとっていること。 ③ 売場の出口などの精算場所で客が一括して代金の支払いを行う形式になっていること。
- 一般的な産業分類の格付
数種類の商品を販売している商店の産業分類は原則として次の方法により決定する。
まず、年間商品販売額のうち、卸売、小売、飲食部門のそれぞれの販売額を比較して、いずれが多いかによって卸売業か小売業又は飲食店かを決定する。次に卸売業か小売業になった場合は、上位5品目の販売額のうち商品分類番号の上位2桁で最も多いものによって中分類業種を決定し、その中分類に属する商品のうち商品分類番号の上位3桁で最も多いものによって小分類業種を決定する。 - 例外的な産業分類の格付
例外的な産業分類の格付けを行っているものは、次のとおりである。
- 48B その他の各種商品卸売業
- 3財(生産財、資本財、消費財)にわたる商品を卸売し、各財別の販売額がいずれも卸売販売額の50%未満で、従業者が100人未満の商店。
- 平成9年調査で「その他の各種商品卸売業」に格付けされた商店。 ただし、従業者数が100人以上となった場合は、一般的な格付けとする。
- 平成9年調査で「各種商品卸売業」に格付けされた商店が、従業者数100人未満となった場合。
- 541 百貨店
衣食住にわたる商品を小売し、その各販売額がいずれも小売販売額の10%以上70%未満で、従業者が常時50人以上の商店。
- 549 その他の各種商品小売業
- 衣食住にわたる商品を小売し、その各販売額がいずれも小売販売額の50%未満で、従業者が50人未満の商店。
- 平成9年調査で「その他の各種商品小売業」に格付けされた商店。 ただし、従業者数が50人以上となった場合は、一般的な格付けとする。
- 561 各種商品小売業
中分類「56飲食料品小売業」の販売額が最も大きい商店で、販売商品の上位5品目に小分類「562~568及び569」のうち3つ以上の商品を小売し、そのいずれもが飲食料品小売販売額の計の50%に満たない商店。
- 48B その他の各種商品卸売業
10.注意事項
平成11年商業統計調査は、平成11年事業所・企業統計調査との同時調査に伴い、既設ではあるが未把握だった対象事業所(平成8年事業所・企業統計調査で商業事業所として把握していて、平成9年商業統計調査で未把握の事業所)の捕捉を行ったこと、また簡易調査として実施したため、調査に用いた商品分類や産業格付け方法が9年調査とは一部異なっていることなどから、9年調査以前の数値とは捉え方が異なっている。
そのため、本文中及び統計表中の数値については今回把握した実数を使用し、増減率・指数については時系列比較を考慮して、9年調査データは11年調査の商品分類で組み替えた数値を、11年調査データについては新規に把握した既設事業所を除いた数値を用いて算出している。このため公表値により算出した値とは一致しない。
ページの先頭へ戻る
- 統計表中の記号
「X」
その数字に該当する商店が1又は2であるため、個々の申告者の秘密が漏れる恐れがあるので、商店数以外の数値を秘匿したことを示したもの。なお、この秘匿によってXが算出される恐れのあるものについては、商店数が3以上のところについてもXとして秘匿する場合がある。
「0.0」
単位未満のもの。
「-」
該当がないもの。 - 構成比については、単位未満を四捨五入しているので、総数と内訳の合計が一致しないことがある。
- この結果内容は県独自で集計したものであり、通商産業省(経済産業省)から公表されるものと相違することがある。
| トップページへ | 利用上の注意 | 調査結果の概要 |
 やまなしの統計へ |
 過去3年間の統計データへ |
